投稿・コラム
投稿日:2021年04月15日
/ 更新日:2023年06月09日
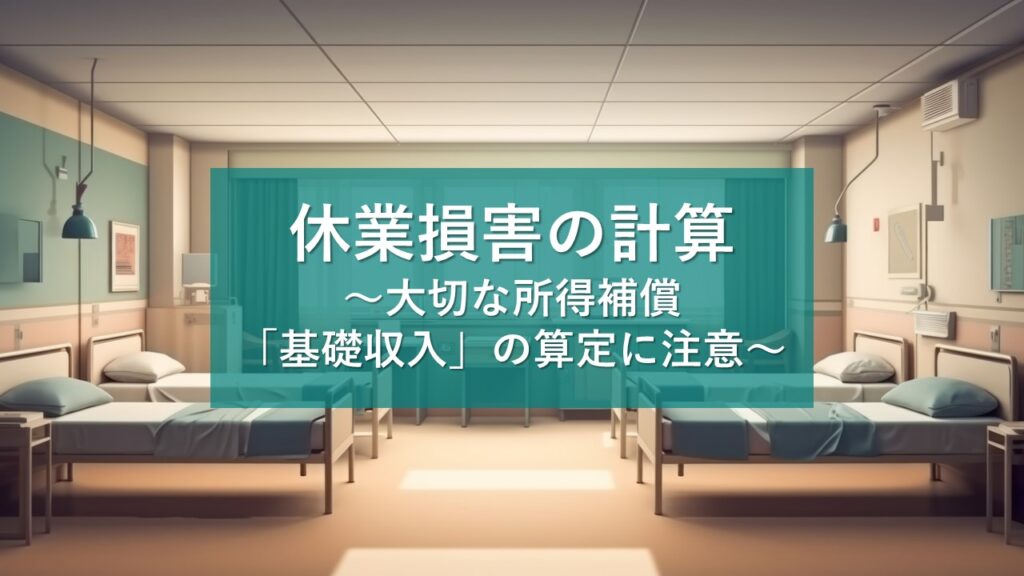
目次
交通事故により仕事を休んだら?
交通事故に遭った時、入院や通院など、ケガの療養のために仕事を休んだり、またケガのせいで今までのように働くことができなくなったりすることがあると思います。
このような交通事故のケガの療養期間中に本来働いて得ることができた収入の喪失を休業損害といいます。
事故がなければ得られたはずの収入(利益)を失っているわけですから、その失った分は事故による損害であるとして、事故の加害者に損害賠償請求することができます。次の項目で、具体的な休業損害の計算方法について整理しました。
休業損害の計算方法
休業損害の計算方法は、下記のようになります。
(1)事故前の収入の日額 ×(2)休業日数 -(3)休業中に支払われた収入
(1)事故前の収入の日額(2)休業日数(3)休業中に支払われた収入については、次に詳しく述べます。
事故前の収入の日額とは
事故前の収入の日額のことを「基礎収入」と言います。要するに、被害者が1日平均どのくらいの収入があるのかを基準に計算することになります。
会社員(給与所得者)の場合
会社員(給与所得者)の場合、一般的には事故前3か月の収入の金額の平均額を基礎収入と考えます。
もっとも、収入に不確定要素の強い職種の場合は、より長期間の平均値を取ったり、季節的な変動のある職種については前年度の同時期の収入を考慮したりします。
事業所得者の場合
個人事業主は給与所得者と異なり、月額の収入が安定したものではなく、かつ、事業の内容によりけがとの関係でどのような影響が出るのか慎重な検討が必要になります。
そこで簡易な計算方法として、事故前の申告所得額を採用し、その日額を基礎収入とすることが多いです。
さらに、個人事業主の場合、休業中も将来の事業継続のためにやむを得ない固定費(家賃や従業員等の給料)も休業損害として請求できます。
家事従事者(専業主婦(夫)や兼業主婦(夫))の場合
交通事故の実務では、家事をすることも労働の一種に含まれます。そして、その基礎収入については、事故の発生した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金を基準にします。
令和4年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金は3,943,500円となりますので、家事ができない日について1日あたり10,804円の休業損害が発生することになります(賃金構造基本統計調査)。
なお、共稼ぎなどの兼業主婦については、現実収入の金額と事故の発生した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金を比較して、いずれか高い方を請求していくことになります。
失業者の場合
失業者については、労働して賃金を得ていないのですから、原則として休業損害の発生は認められません。
例外的に、療養期間に再就職したであろう蓋然性が立証された場合には休業損害の発生が認められます。この場合、被害者の予測される将来の職業、性別、年齢、学歴から蓋然性の高い基礎収入を認定することになります。
学生の場合
学生について、アルバイト収入がない限り、原則として休業損害は認められません。
しかし、就職が内定していた場合など、しかるべき時期に就労して収入を得ることができたであろう場合には、就労を開始したであろうと認められる時期以後の休業損害が認められる可能性があります。
休業日数として認定できるか
一般に、休業日数とは、事故日から症状固定(治療を続けても、その効果を期待しえない状態)までの期間において療養のために現実に休業した日数のことを言います。
また、休業の事実があれば無条件で休業損害が発生するわけではなく、ケガの程度や被害者の従事している業務の内容から相当な休業日数を判断することになります。
例えば、主にデスクワークをしている被害者が足の小指を骨折して、症状固定まで仕事を休み続けたとします。この場合、休んだ日全てに休業損害が発生するのではなく、通院などの必要の為に休んだ時間にのみ休業損害としての請求ができることになります。
有給休暇を取得して休業した場合請求できるか
よくある質問として、「療養のために有給休暇を取得した場合は、その分の休業損害は請求できないのか?」という質問を受けることがあります。当然、本来他のために充てることができた有給休暇を事故のために使用せざるを得なかったのであるから、取得した有給休暇についても休業日数に含めることができます。
交通事故のご相談は「いかり法律事務所」へ
休業損害は、基礎収入の基準によりその金額が大きく異なることがわかります。そして、基礎収入はその人の職業によるところがあり、また、金額も決まったものでないため、専門的な知見が必要になります。
休業損害についてもまずは、加害者の保険会社との交渉の中で、その損害賠償額を請求していくことになります。しかし、保険会社としては、自己に交渉が有利になるように交渉するのが一般的であります。そうしたときに、自分の知らない間に相手方に有利なように話が進められている場合があります。
被害者の方が、弁護士特約などに加入していれば、弁護士費用は自分の保険会社が負担してくれますので、まずは弁護士に相談するのが良いでしょう。当法律事務所には多数の交通事故の解決実績がありますので、休業損害をはじめ交通事故について少しでも気になることがあればお気軽にお問合せ下さい。